天正17年(1589)8月、近江国浅井郡(今の滋賀県)では中野村と青名村・八日市村(いずれも今の長浜市)との水論から刃傷事件が発生し、豊臣政権の「喧嘩停止令」に背いたとして、3村から1人ずつ成敗されることになりました。他の村人たちの身代りを自ら願い出た中野村清介に対しては、当時から奉行人や惣村のさまざまな援助があり、今に至るまで顕彰が続けられています。
義民伝承の内容と背景
しかし、その後もこれらの村々での争いは続き、ついに天正17年(1589)8月17日には、井頭での口論が激化して互いに刃傷に及ぶ事態となったことから、豊臣政権の「喧嘩停止令」に違反する「曲事」であるとして、中野・青名・八日市の各村から1人ずつが成敗(処刑)されることになりました。
中野村では村人一同が了福寺に集まって食事をし、山盛りの飯を1粒でも取り落とした者を身代わりに差し出すことに決めましたが、このとき清介はわざと椀を逆さにして飯を転がすと、羽織っていた着物を脱いで、下に着込んでいた白装束の姿になり、自ら身代りになることを皆に告げたと伝えられています。
豊臣秀次の奉行人で佐和山城主の堀尾吉晴は、この清介の潔さにいたく感動し、清介の処刑に先立ち、所望があれば存分に叶える旨を約束したところ、清介は屋敷2か所を末代まで申し請けたいと述べました。
そこで堀尾吉晴は、望みにしたがい屋敷を破却せずに残すことはもちろん、清介の娘・いわの養育や遺産である屋敷・田畑に対する扶助、夫役の免除についても特段の配慮をするよう、惣村に対して「疎略仕間敷候」と命じており、地元には「中野村清介跡目岩女かたへ」と名宛人が記された堀尾吉晴の花押入りの沙汰状が残ります。
こうして中野村の惣代に立てられた清介は、村はずれの墓地の樫の木の下で処刑されましたが、いつしか墓地の中には表面に「俗名清介 法名釈静西」、右側面に「天正十七年八月十九日 為村身代り死」と刻む清介の墓碑が建てられたほか、昭和6年(1931)には清介の徳を讃える「義人清介氏之碑」が村民の手によりつくられました。今でも命日とされる8月19日に感謝祭が開かれ、子孫の家では地域作業が免除されるなど、清介の遺芳を偲ぶことができます。
参考文献
『豊臣平和令と戦国社会』(藤木久志 東京大学出版会、1985年)pp.81-82
『虎姫のむかし話』(虎姫むかし話編集委員会編 虎姫町公民館、1979年)pp.130-131
『東浅井郡志』 巻3(黒田惟信編 滋賀県東浅井郡教育会、1927年)p.869
『東浅井郡志』 巻4(黒田惟信編 滋賀県東浅井郡教育会、1927年)pp.77-78
義人清介氏之碑の場所(地図)と交通アクセス
名称
義人清介氏之碑
場所
滋賀県長浜市中野町地内
備考
「義人清介氏之碑」は、虎御前山の南麓を走る水路沿いにあり、石碑のすぐ上は「中野村清介の墓」がある共同墓地となっています。マイカーの場合、北陸自動車道「小谷城スマートインターチェンジ」からおよそ3分の距離にあり、滋賀県道263号丁野虎姫長浜線の最寄り交差点を南東に50メートル進めば到着できますが、この交差点には何の目印もありません。もしも県道を長浜市街地方面から北上するのであれば、「世々聞橋」の東側を並行する「馬橋」を経て田川を渡り、「世々聞長者流水遺功碑」や「専宗寺」の前の市道を北に500メートルほど道なりに進むのがわかりやすいルートです。専用の駐車場はありませんが、30メートル離れた場所に石地蔵などを祀るお堂と親水施設があり、ここに3台程度駐車できるスペースがあります。公共交通機関を用いる場合は、JR北陸本線「虎姫駅」から北に歩いて15分ほどです。
関連する他の史跡の写真
 中野村清介の墓
中野村清介の墓 了福寺
了福寺
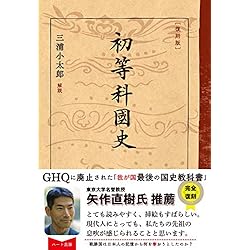 [復刻版]初等科国史
[復刻版]初等科国史
