江戸時代初期の元和5年(1619)、近江国(今の滋賀県)の日野山をめぐる山論を解決するため、馬見岡綿向神社の境内で、熱した鉄の斧を手で握って神前に戻すことができた方を勝訴とする「火起請」による裁判が行われました。地元には勝訴して入会権を守った音羽村(今の蒲生郡日野町)庄屋・喜助の顕彰碑が建つほか、喜助の子孫が神社を参拝する「鉄火祭」も毎年のように続けられています。
義民伝承の内容と背景
ところが、江戸時代に入って日野山が幕府直轄地になると、蒲生郡日野町などの「東郷九ヵ村」(今の日野町)が年貢を請け負う代わりに入山を許される方式に改められたため、立入りができなくなった石原村など「西郷九ヵ村」(今の日野町・東近江市)が反発し、多数の村々を巻き込んだ山論に発展しています。
この訴訟は「大坂の陣」などの影響もあって遅々として進まず、出訴からおよそ10年を経た元和5年(1619)になって、石原村(今の日野町)で養われていた浪人の角兵衛が、「火起請」という方法により解決することを庄屋に提案しました。
古代の盟神探湯と同様、室町時代のころには、訴訟当事者が神前で煮えたぎる湯の中に手を入れて、その際の火傷の具合を見て正邪を判断する「湯起請」が盛んに行われていました。
まだ中世の遺風が残る江戸時代のはじめにも、熱した鉄を手のひらに受けられるかどうかで正邪を判断する「火起請」あるいは「鉄火起請」とよばれる「神判」が各地で行われていた記録があります。
『山論鉄火裁許之訳書』によれば、このとき「読書等も相応ニ致才知有者」である角兵衛が、「長々敷御裁許を御待被成候ゟ、神慮に任せ、綿向の神前に而鉄火ヲ取、無事ニ取得たる方を利とし、不取得方を非と致候ハヽ、早速落着可致候、若シ此義に極り候ハヽ、私儀数年当村之御憐愍を請、御世話に罷成候御恩報として、鉄火を取候役可相勤」と、長年にわたり幕府の裁許を待つよりも、むしろ神意に委ねて綿向神社で火起請をしたほうが早期解決の見込みがあることや、もしも火起請をするのであれば村への恩返しとして自ら鉄火を取る役目を引き受ける意思があることを語ったといいます。
そこで西郷から東郷に火起請の件を持ちかけたところ、東郷の寄合で誰も鉄火の役に志願する者がないのを「気之毒」に思った村井横町(今の日野町)の九郎左衛門が「神は正直を照し玉ふ、何の恐か候ハん」と言って役目を引き受けたため、当事者双方合意の上として幕府に伺いを立て、火起請による裁判が認められることになりました。
このころ、音羽村庄屋の喜助は弁舌に優れ、役所をはじめ村々との交渉事も一手に引き受けていましたが、喜助に嫉妬した西郷の人間が「是まてハ何事も利口に言廻され候得共、鉄火は取れ申間敷」と嘲笑しため、挑発に乗った喜助は「拙者鉄火を取見せ可申」と返答し、本人たっての希望で、東郷で鉄火を取る役が急遽九郎左衛門から喜助に変更となっています。
西明寺・正明寺・金剛定寺の三ヵ寺では、わずかな柴草のために人命が失われることを嘆いて鉄火裁判をやめさせようとしましたが、すでに江戸の老中の決裁を経ていたためにどうすることもできず、元和5年9月18日、とうとう鉄火裁判の当日を迎えました。
この日、綿向神社の神前に用意された棚には、それぞれの村から提供された、斧の形をした鉄のかたまりが置かれ、その5間(およそ9メートル)ほど南側には、東西に分けて炭火を起こす炉が設けられ、待機していた鍛冶師が鉄を受け取ると、江戸からやってきた角田主馬・小川吉右衛門ら幕府役人の検視の下、双方同じように焼き赤らめたといいます。
そして刻限になり、手のひらにへぎ板を敷いて鉄を受け取ろうとした矢先、監視していた検視の役人は、鉄に何か不正な仕掛けがないかと用心して、東郷から提供された鉄を西郷の者に、西郷から提供された鉄を東郷の者に渡すよう命じました。
白木綿の衣裳で現れた喜助と角兵衛は、それぞれ赤く熱せられた鉄を手のひらに受け取りますが、喜助が3間(およそ5.5メートル)ほど走って元の棚に鉄を投げ入れたのに対し、角兵衛は手のひらが焼けただれてその場で鉄を取り落とし、逃げようとしたところを役人に捕まった上、翌日には町内を引き廻されて西之野の仕置場(今の日野町上野田の雲雀野という)で磔に処せられたということです。
『山論鉄火裁許之訳書』には「此角兵衛聊奸智有者故、無益之事を言出し人を苦んとすれと、天罰不遁却而其身を亡し事可恐事なり、又歟様之事も有んかと、鉄火を取替被渡候御上の明察可恐賞」とあり、どうやら角兵衛は鉄に混ぜものをして熱くならない細工をしていたたものの、役人がそれを見破って事前に鉄を交換したため、悪知恵がかえってあだとなり身を滅ぼしたものといえます。
こうして日野山をめぐる山論は東郷の勝訴となり、幕府からも褒美として喜助に蔵王村(今の日野町)砥山、九郎左衛門には村井町の南に3畝あまりの田地が与えられ、俗に「鉄火田」とよばれたということです。
その後、喜助の子孫は神恩感謝のため、裁判のあった9月18日(新暦では10月18日)早朝に綿向神社を参拝する「鉄火祭」を毎年欠かさずに続けるようになりますが、江戸時代後期の国学者・平田篤胤も著書『古史伝』に「喜助が家より。毎年此社へ献物して。是を銕火祭と云なり。」と記し、その出典に『綿向神社名跡記』という書物を挙げています。
また、かつての東郷各村の入会権を根拠として昭和30年(1955)に設立された綿向山財産区・大山財産区は、昭和42年(1967)に滋賀県知事・野崎欣一郎題字の「共有山林顕彰碑」を綿向神社境内に建立して喜助の偉業を顕彰しているほか、「さつき寺」として知られる町内の雲迎寺境内にも、別に「喜助翁鉄火記念」と刻む石碑が存在します。
参考文献
『近江蒲生郡志』巻8(滋賀県蒲生郡役所編 滋賀県蒲生郡役所、1922年)
『近江日野町志』巻上(滋賀県日野町教育会編 臨川書店、1986年)
『百姓一揆と義民の研究』(保坂智 吉川弘文館、2006年)
『日本神判史 盟神探湯・湯起請・鉄火起請』(清水克行 中央公論新社、2010年)
『近江日野の歴史』第3巻 近世(日野町史編さん委員会編 滋賀県日野町、2013年)
『近江日野の歴史』第8巻 史料編(日野町史編さん委員会編 滋賀県日野町、2010年)
共有山林顕彰碑の場所(地図)と交通アクセス
名称
共有山林顕彰碑
場所
滋賀県蒲生郡日野町村井705
備考
「共有山林顕彰碑」は、馬見岡綿向神社境内の正面向かって右手の参道沿いに建てられており、表面には鉄火裁判を含む建碑の経緯が記されています。碑へのアクセスは、マイカーの場合、名神高速道路「蒲生スマートIC」で降りて国道477号を南東におよそ20分、公共交通機関の場合、近江鉄道水口・蒲生野線「日野駅」から近江バス(北畑口行き)乗車10分、「向町」バス停で下車して北へ徒歩5分です。なお、馬見岡綿向神社の境内入口近くに無料の参拝者用駐車場があります。
関連する他の史跡の写真
 喜助翁鉄火記念碑
喜助翁鉄火記念碑
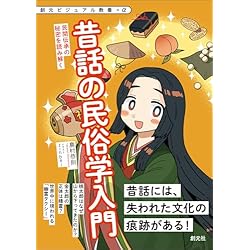 昔話の民俗学入門: 民間伝承の秘密を読み解く
昔話の民俗学入門: 民間伝承の秘密を読み解く
