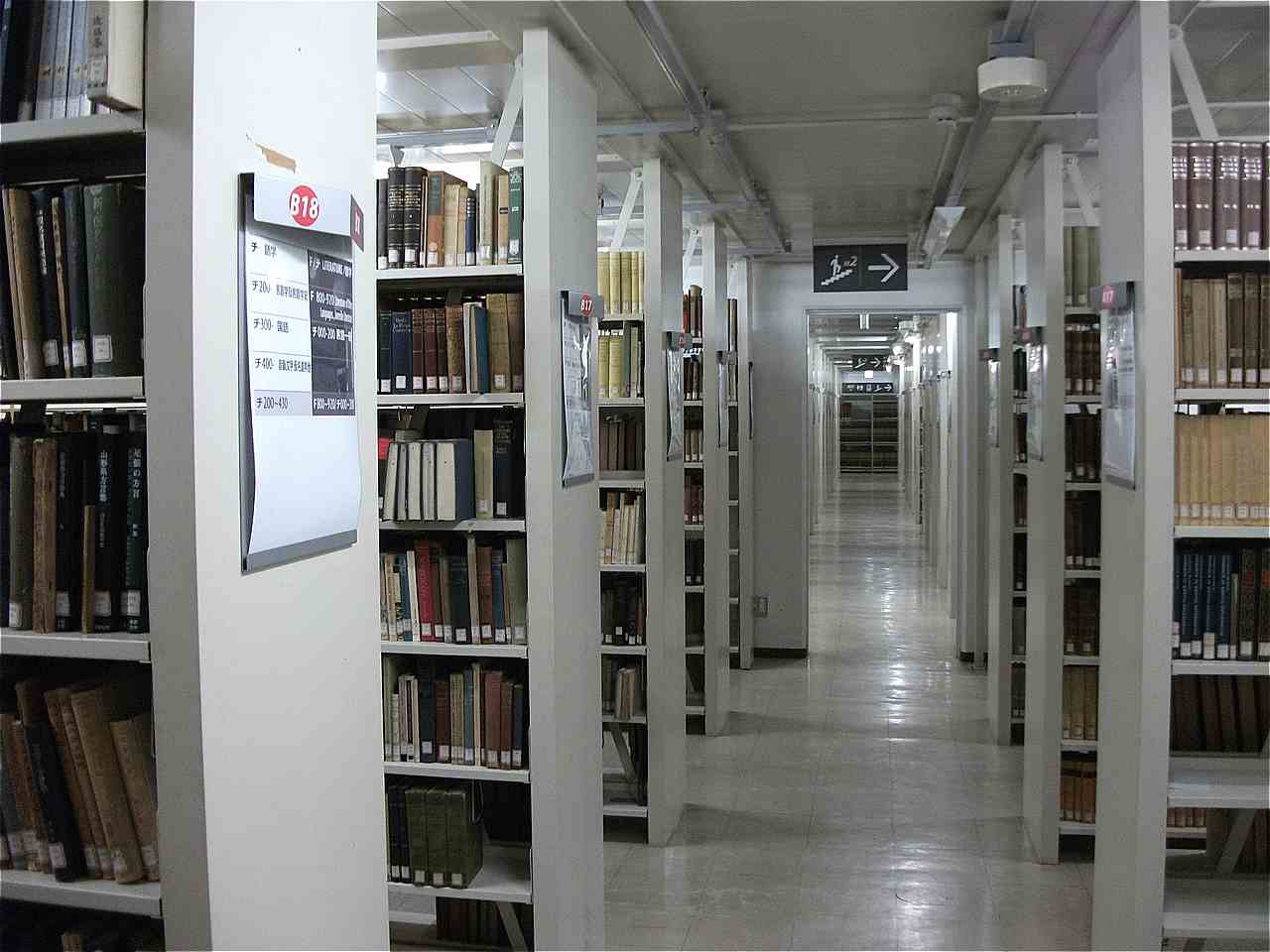幕府久美浜代官であった和田主馬は、天保の飢饉に際して年貢を減免するなど善政を施したため、郡内各地に若宮として祀られました。現在も矢田八幡神社には和田主馬の名を刻んだ若宮神社の石塔が残されています。
伝承の内容と背景
在任中に発生した「天保の飢饉」に際しては、上納米を3分の1に減免の上で5か年賦として百姓の負担軽減を図るとともに、高100石につき銀300匁の救助金を下付したと伝えられます。なお、『佐濃村誌』では、これを天保2年(1831)の「卯歳の大飢饉」のこととしています。
このような和田主馬の善政に感謝した丹後国熊野郡(今の京都府京丹後市)の人々は、郡内各地に「若宮神社」の小祠を建てて、和田主馬を神として祀りました。現在も京丹後市の矢田八幡神社の境内には、天保7年(1836)の紀年銘をもつ「若宮神社」の石塔が残されています。
参考文献
『日本海地域史研究』第2巻(日本海地域史研究会編 文献出版、1981年)
若宮神社の場所(地図)と交通アクセス
名称
若宮神社
場所
京都府京丹後市久美浜町佐野864番地
備考
「若宮神社」は、北近畿豊岡自動車道「豊岡出石インターチェンジ」から車で30分ほどの、京丹後市久美浜町佐野に鎮座する「矢田八幡神社」の境内の一角にあります。国道312号「小桑口」交差点に接する表参道の石段を登ると、神門の下で参道が直角に曲がる部分があり、正面に「若宮神社」、右側面に「天保七申 和田主馬神奉祠」と彫られた石塔がこの場所に建てられています。
関連する他の史跡の写真
 久美浜代官所跡
久美浜代官所跡
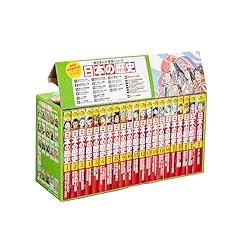 角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 全16巻+別巻5冊定番セット
角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 全16巻+別巻5冊定番セット