 義民の史跡
義民の史跡 義民宗次郎の碑(畝傍村宗次郎と旗本神保氏領強訴)
明和5年(1768)、大和国(今の奈良県)では凶作をきっかけに旗本・神保氏領内の9か村、千人あまりの百姓が池尻陣屋へ強訴に及び、不納銀の取立て免除などの要求を代官に認めさせました。その後の厳しい吟味に...
 義民の史跡
義民の史跡  義民の史跡
義民の史跡  義民の史跡
義民の史跡  書誌その他
書誌その他  義民の史跡
義民の史跡  義民の史跡
義民の史跡  義民の史跡
義民の史跡  義民の史跡
義民の史跡  義民の史跡
義民の史跡  義民の史跡
義民の史跡  先賢・循吏の史跡
先賢・循吏の史跡 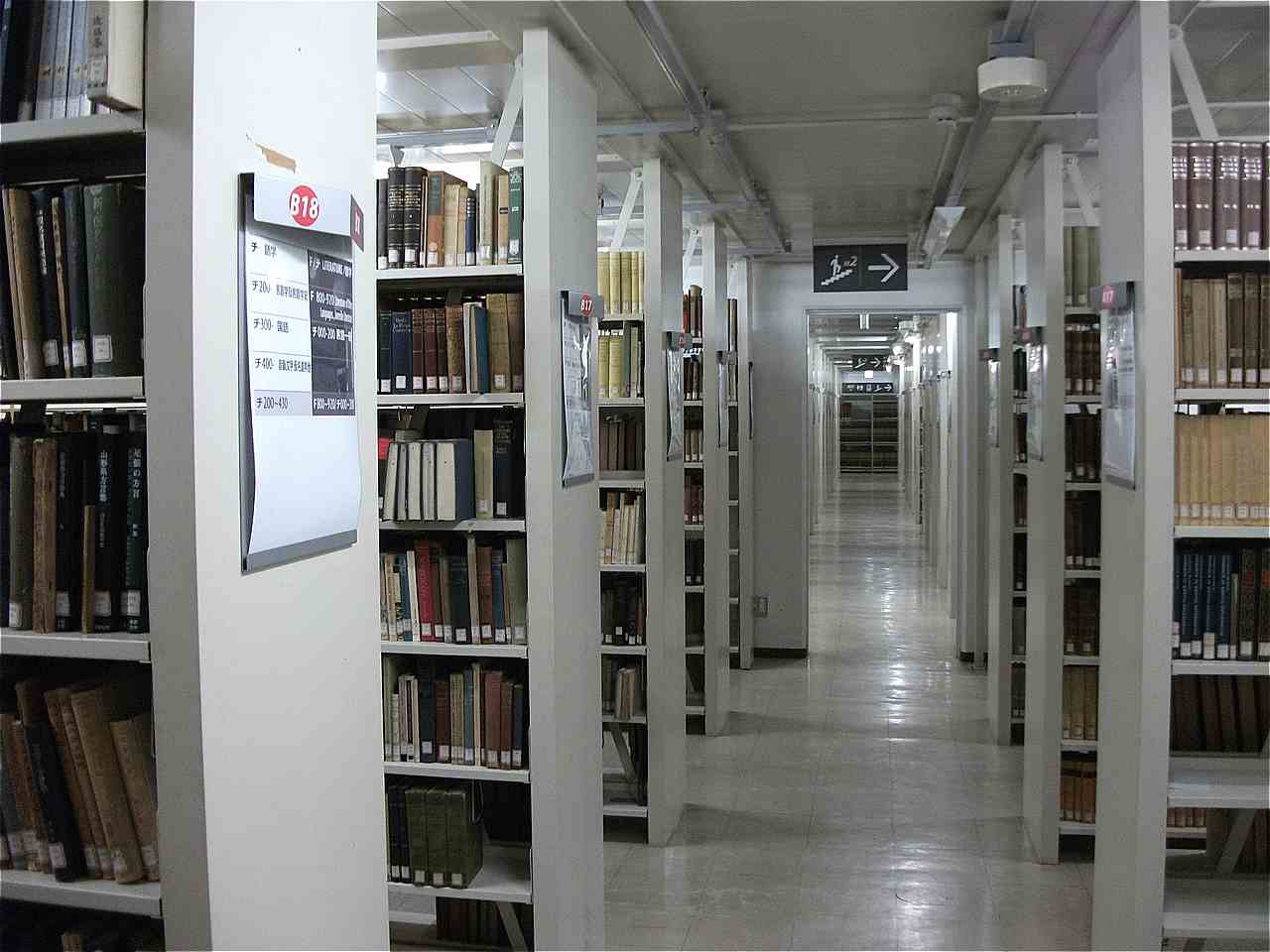 書誌その他
書誌その他